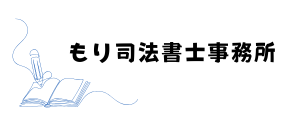【手書きの遺言書と公正証書の遺言書の違い2/2】
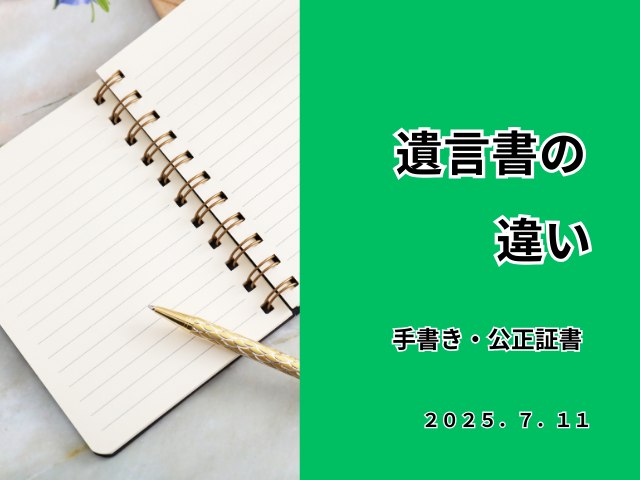
手書きの遺言書と公正証書の遺言書の違いについての解説の続きになります。
遺言書は、手書きのものも、公正証書のものも効力に優劣はありません。
手書きの遺言書のルールは以前ご説明しましたが、意外とルールは簡単に思われたのではないでしょうか。
となると、手書きの遺言書で作成した方が楽そうですが、実はそうではありません。
手書きの遺言書は、相続の手続にそのまま使用することはできません。
遺言書作成後、遺言を書かれた方が亡くなると、遺言書に従って手続を開始することとなりますが、遺言書の「検認」という手続をまずしなければなりません。
「検認」とは、手書きの遺言書を家庭裁判所に持っていき、封を開ける作業のことをいいます。
また、検認手続を家庭裁判所にて行うために、戸籍を収集する必要があります。
検認手続に際して、事前に遺言者の相続人全員に検認手続がされる日時場所について通知が届き、相続人が検認に立ち会う可能性もあります。
このように、手書きの遺言書は一見楽そうですが、実は、検認手続が必要であり、その手続は想像以上の時間と労力を要します。
一方、公正証書の遺言書であれば、遺言書の作成の際に公証役場に行く必要がありますが、作成してしまえば「検認」のような手続は一切不要です。
また、公正証書の遺言書を作成する際にも戸籍は必要になりますが、手書きのものを作成するのと比べて少ない戸籍で済みます。
公正証書の遺言書を作成すると、原本は公証役場にて保管され、法的効力のある写しが発行され、その写しが相続手続でそのまま使用することができます。
このように、手書きの遺言書と公正証書の遺言書では、遺言書が亡くなった後の相続手続のタイミングで大きな違いがでてきます。
遺言書を作成する際は、単に文章を書くだけではなく、なにかしらの手続が必要となります。
そのなにかしらの手続を先にしておくのか、後回しにするのか。
財産のスムーズな承継のためにも、必要な手続を先に終わらせておきましょう。
そのためにも、遺言書を作成する際は、公正証書にて作成することをオススメいたします。
投稿日:2025年07月11日